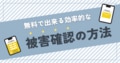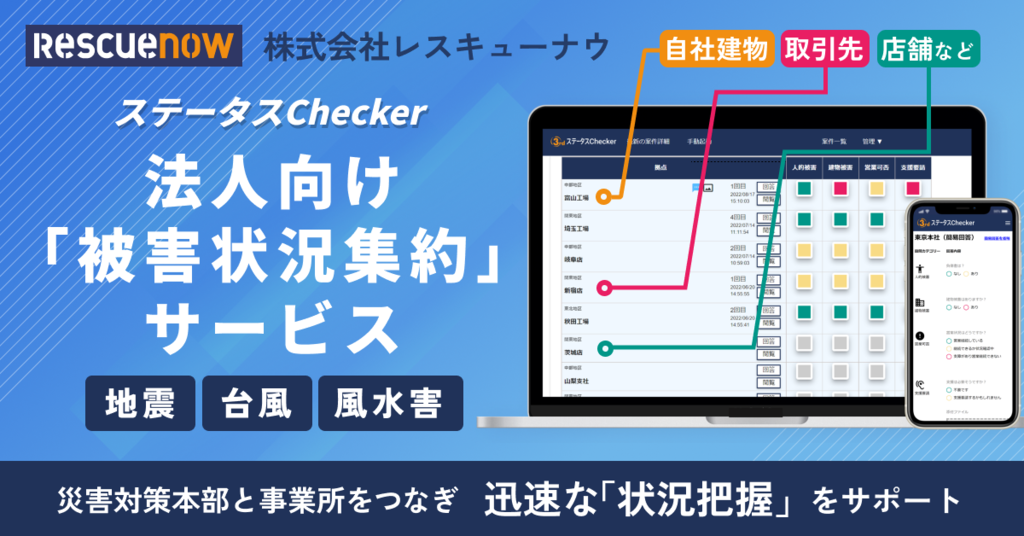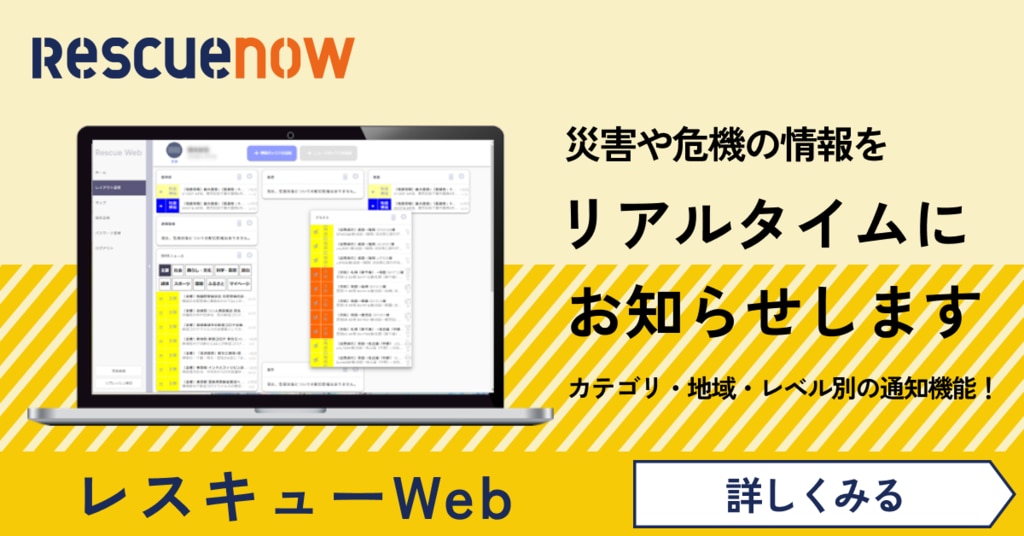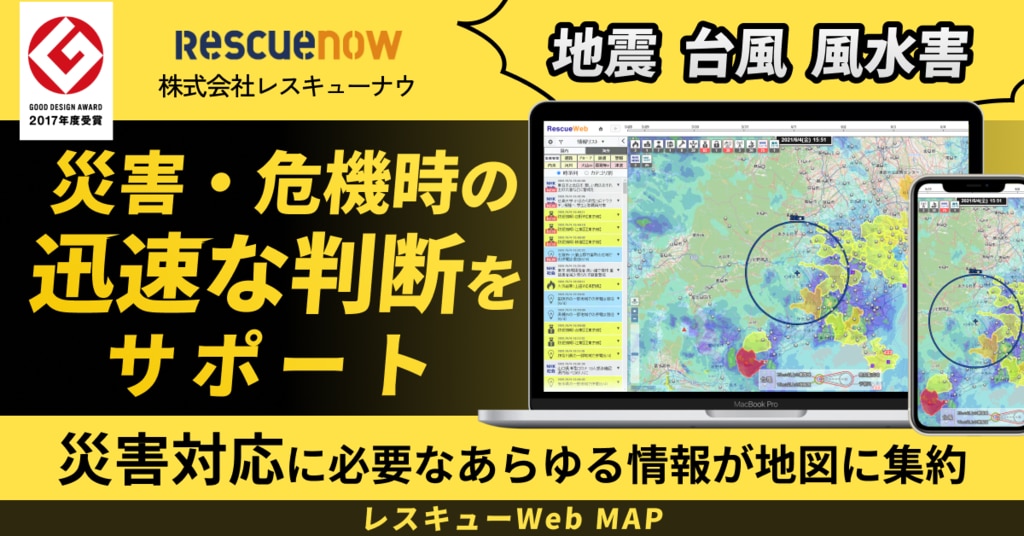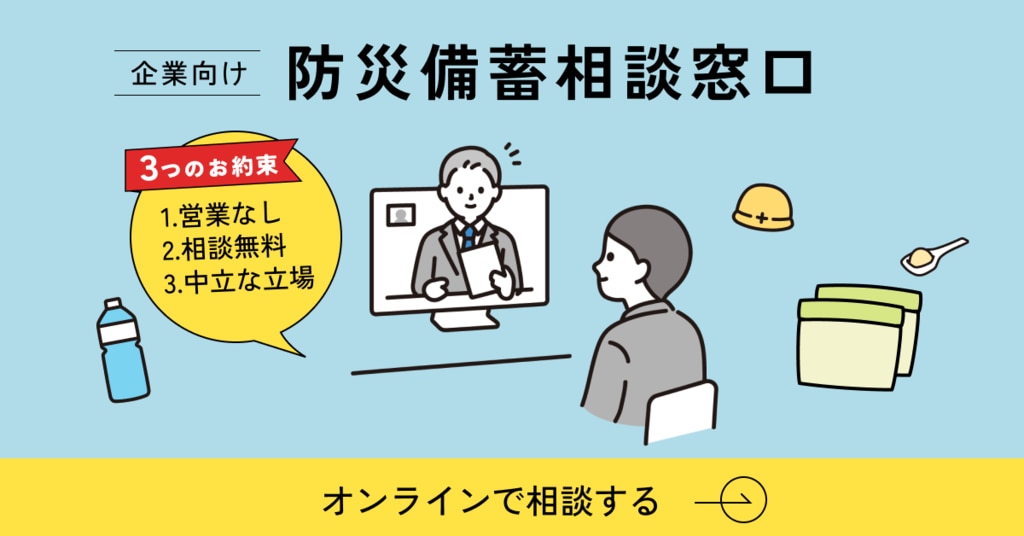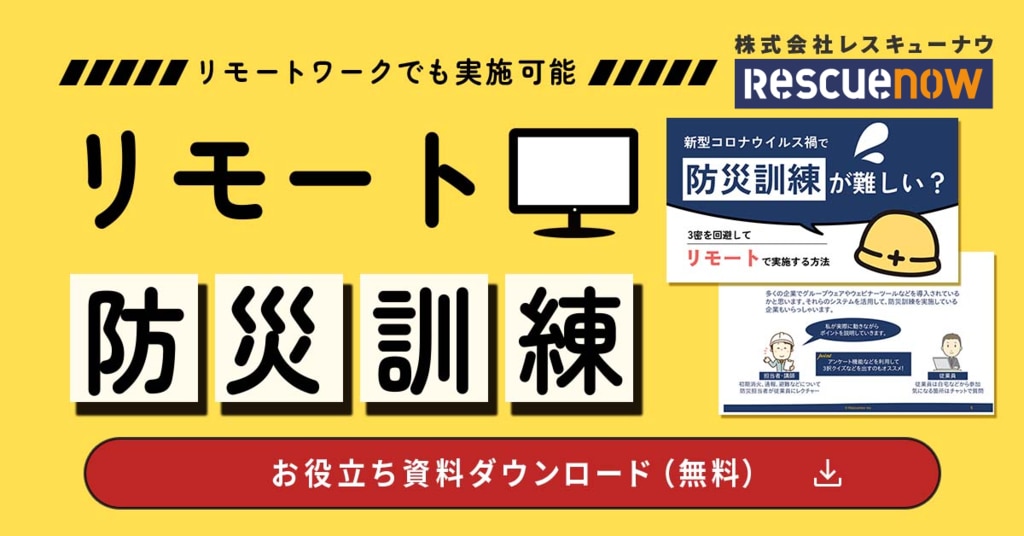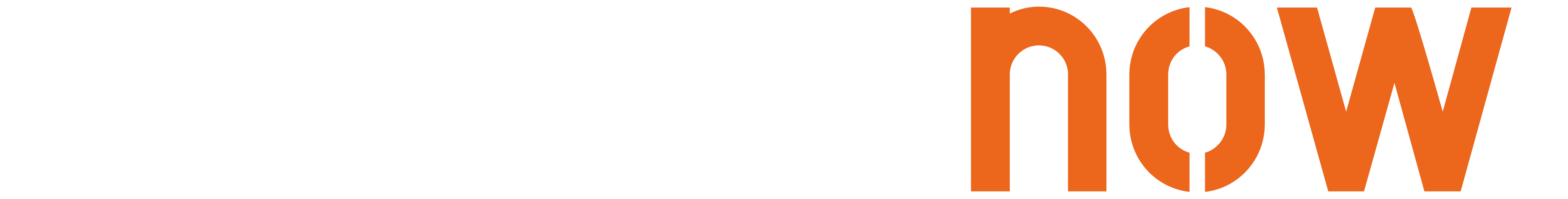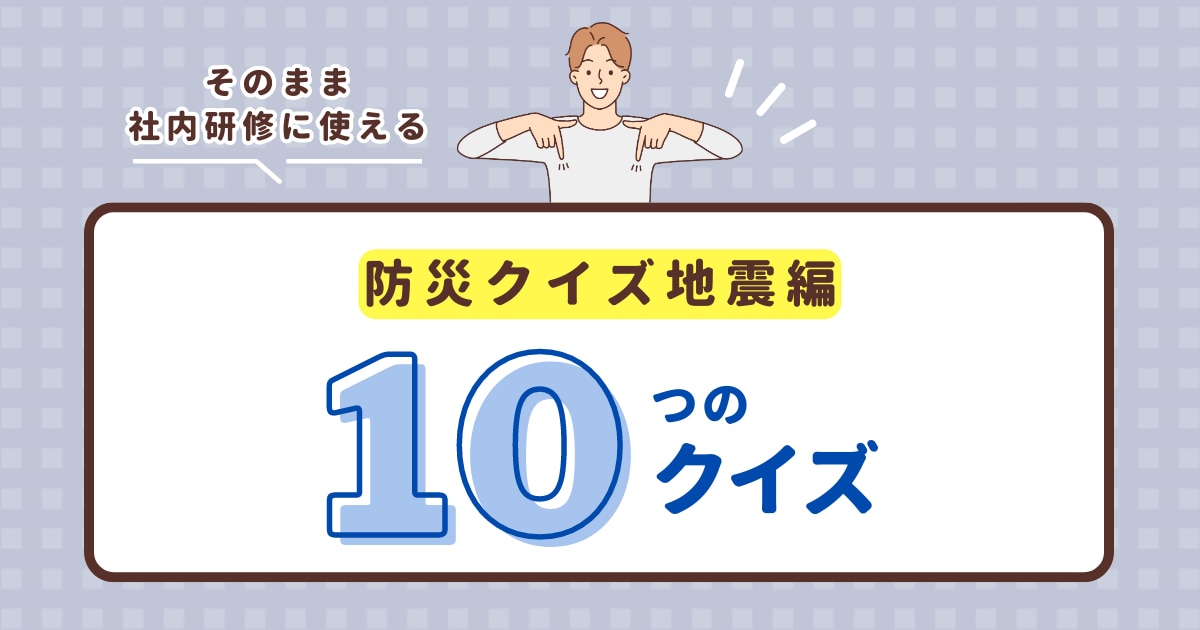
楽しく防災知識が学べる!防災クイズ(地震編)
いざという時に従業員の安全を確保するためには、定期的な防災訓練が必須です。ただ、日常業務に追われる中、防災訓練を繰り返し実施するのはハードルが高いと思います。
そのような場合にオススメなのが「防災クイズ」です!
全社員が時間を合わせて実施する防災訓練に比べて実施負担が圧倒的に少なく、クイズ形式なので楽しく学ぶことが出来ます。
\ 研修で使いたい方、もっと解きたい方はこちら! /
この記事の目次[非表示]
- 1.防災クイズの意義
- 2.防災クイズの活用方法
- 2.1.WEBフォームを活用する方法
- 2.2.安否確認システムを活用する方法
- 3.防災クイズ地震編 全10問(解説付き)
- 3.1.第1問 緊急地震速報が鳴った場合、最初にすべきことは何でしょう?
- 3.2.第2問 エレベータ搭乗中に地震に遭ったら何をするべきでしょう?
- 3.3.第3問 勤務先からの避難について次のうち望ましくない選択肢はどれでしょう?
- 3.4.第4問 倒れている人を発見した場合、最初にすべきことは何でしょう?
- 3.5.第5問 心肺蘇生について正しい選択肢は、次のうちどれでしょう?
- 3.6.第6問 119番通報の際、最初に聞かれることは次のうちどれでしょう?
- 3.7.第7問 大人ひとりが1 日に必要な飲料水は何リットルでしょう?
- 3.8.第8問 大人ひとりが1 日あたり必要な備蓄トイレの数は何回分でしょう?
- 3.9.第9問 災害時に徒歩で帰宅できる距離は何㎞まででしょう?
- 3.10.第10問 災害時の情報の取り扱いについて正しい選択肢はどれでしょう?
- 4.最後に
防災クイズの意義
実際に体を動かす訓練は非常に重要ですが、実施回数は年に1~2回ぐらいかと思います。
年に1~2回では間隔が空きすぎてしまい、せっかく教わった防災知識を忘れてしまっている従業員も多いのが実態です。
そこで、防災クイズを活用して定期的に復習することをオススメします。
また、正解率などで自社の防災レベルを測ることも出来るため、正解率が低かった問題について次回の防災訓練で重点的にフォローアップする等の取り組みもオススメ!
防災クイズの活用方法
防災クイズを社内で活用する方法について2つご紹介します。
WEBフォームを活用する方法
Googleフォーム等でクイズを作成し、業務の隙間時間で従業員に回答してもらう方法。
集計された点数で従業員の防災レベルを測り、正解率のアップをBCP活動計画などに盛り込むこともオススメです。
安否確認システムを活用する方法
普段実施している安否確認システムの応答訓練で、防災クイズを出題する方法。
安否確認システムの応答方法を習熟するだけでなく、防災知識も身に付くため、一石二鳥の方法です。
また、人間の心理として、クイズを出題されると答えが気になって思わず回答してしまうことがあると思います。安否確認訓練の応答率が上がらず悩んでいる場合、防災クイズを出題することで応答率が上がるかもしれません。
防災クイズ地震編 全10問(解説付き)
一般従業員や新担当者向けの基礎的なクイズを全10問ご用意しました。
第1問 緊急地震速報が鳴った場合、最初にすべきことは何でしょう?
A:机の下や物が無い場所に逃げる B:火を消してガス栓を閉める
C:走って屋外に避難する D:家具が倒れないようにおさえる
〈正解〉A. 机の下や物が無い場所に逃げる
緊急地震速報が鳴ってから強い揺れが来るまでの時間は、数秒~数十秒と言われています。
そのため、瞬時に身の安全を確保することが何より重要です!
なお、机など隠れる場所がない場合、大きな家具や窓ガラスなどから離れましょう。物が無い廊下やエントランス、エレベーターホールへの退避も有効な場合があります。
第2問 エレベータ搭乗中に地震に遭ったら何をするべきでしょう?
A:地上に出るため1 階を押す B:最寄り階を押す
C:全部の階を押す D:非常ボタンを押す
〈正解〉C. 全部の階を押す
いち早くエレベーターから降りるために“すべての行先階ボタン”を押して、最初に停止した階で降りてください。
万が一エレベーター内に閉じ込められた場合は、エレベーターの非常ボタンを押し、管理室や保守点検業者と連絡を取りましょう。
第3問 勤務先からの避難について次のうち望ましくない選択肢はどれでしょう?
A:階段を使って避難する B:ヘルメットをかぶって避難する
C:地域の市民向け避難所に行く D:ビルが無事なので留まった
〈正解〉C. 地域の市民向け避難所に行く
避難所は地域の学校などが指定されていますが、これは自宅にいられなくなった地域住民が一定期間の避難生活を過ごす場所です。
地域住民以外の受け入れは想定されていないため、耐震ビルへの入居や備品の転倒防止、防災備蓄品を準備して社内で数日間留まれるようにしましょう。
第4問 倒れている人を発見した場合、最初にすべきことは何でしょう?
A:意識、反応があるか確認する B:救急車を呼ぶ
C:AED を取りに行く D:呼吸を確認する
〈正解〉A. 反応があるか確認する
東京消防庁が公開している手順は、以下の通りです。
- 肩を優しくたたきながら3 回ほど大声で呼びかける(反応があるか確認)
- 反応がない場合、大きな声で周囲の人へ119 番通報と AED 搬送を依頼する
- 胸の動きを見て、普段通りの呼吸があるか確認する
- 呼吸がない場合、普段通りの呼吸でない場合は、すぐに胸骨圧迫を行う
- AED が到着次第、 AED を利用する
※倒れている人に駆け寄る際は、周囲の安全も確認しましょう。
※反応や普段通り呼吸の有無を判断できない場合は、迷わず②からの手順を実行します。
第5問 心肺蘇生について正しい選択肢は、次のうちどれでしょう?
A:胸骨圧迫は心臓のある左側を押す B:どんな時も必ず人工呼吸を実施する
C:大量出血の場合は止血を優先する D:AED が到着しても胸骨圧迫を優先する
〈正解〉C. 大量出血の場合は止血を優先する
じわじわにじみ出す程度の出血なら心肺蘇生を優先しますが、真っ赤な血液が噴き出すような出血の場合は止血を最優先します。
また、AEDが到着した場合は、胸骨圧迫を継続しながらAEDを装着する必要があります。ただし、AEDから「解析中です」とアナウンスがあった際と、電気ショックを行う際は、胸骨圧迫を一旦中断する必要があります。
日本医師会ウェブサイト「心肺蘇生法の手順」がわかりやすくてオススメです。
第6問 119番通報の際、最初に聞かれることは次のうちどれでしょう?
A:火事ですか?救急ですか? B:救急車が向かう住所は?
C:倒れている人の容態は? D:あなたのお名前と連絡先は?
〈正解〉A. 火事ですか?救急ですか?
総務省消防庁が公開している手順は、以下の通りです。
- 火災か救急かを聞かれるので伝えてください。交通事故ならその旨も。
- 場所を聞かれるので住所や交差点名、建物の名前など含めて伝える
- 傷病者の年齢、性別、どのような容態かを伝える
- 通報者の名前と電話番号を伝える
消防は救急車をいち早く向かわせるため、容態などの状況より先に「場所」を尋ねます。
①と②の回答だけでもまずは出動してくれますので、消防からの質問に落ち着いて回答するよう心がけましょう。
第7問 大人ひとりが1 日に必要な飲料水は何リットルでしょう?
A:1 リットル B:3 リットル C:5 リットル D:10 リットル
〈正解〉B.3 リットル
災害時、大人ひとりが必要な飲料水は、3 リットルと言われています。
多く感じる人もいるかもしれませんが、保存食は種類によって通常の食事よりも水分量が少ないものもあり、夏季は冷房が止まる可能性などもあることから、普段飲んでいる量よりも多く備蓄しておくことがオススメです!
また、飲料水は、調理、傷口の洗浄、歯磨き、洗顔などにも活用できます。災害時は飲料水を出来るだけ無駄なく活用しましょう!
第8問 大人ひとりが1 日あたり必要な備蓄トイレの数は何回分でしょう?
A:1 回分 B:3 回分 C:5 回分 D:7 回分
〈正解〉C.5 回分
必要なトイレの数は、1 日あたり 5 回(大 1 回、小 4 回)と言われています。
通常、水は約3 日間、食事は約 7 日摂らなくても生きられると言われています。ただ、トイレは
1 日と我慢できません。
なお、使用済み便袋の処理方法も考えておきましょう!大災害時はゴミ収集が来ないため、敷地やビル内に保管しておく必要があります。食事や睡眠をとる場所に保管するわけにもいかないため、あらかじめ社内やビル管理会社とよく相談のうえ検討しておきましょう。
第9問 災害時に徒歩で帰宅できる距離は何㎞まででしょう?
A:約5km圏内 B:約10km圏内 C:約15km圏内 D:約20km圏内
〈正解〉B. 約10km圏内
災害時は、平時よりも道路が非常に混雑し、道路や橋が通行止めになるなどして迂回しなければいけない場合も想定されます。
そのため、災害時に徒歩帰宅できる距離は、おおむね10km 圏内が限界と言われています。
移動前には経路の情報を集め、防災用品を持参するなど入念に計画・準備しましょう。職場に履きなれたスニーカーを一足用意しておくことをオススメします。
なお、東京都などでは徒歩帰宅による混雑で将棋倒しなどの危険があること、72時間は救助活動に専念する必要があることなどから、3日間は職場に留まることを条例化しています。
第10問 災害時の情報の取り扱いについて正しい選択肢はどれでしょう?
A:被災者のツイートを急いで拡散した B:SNS の投稿時刻で最新情報か確認した
C:画像付きの投稿なので本当だと信じた D:情報の真偽について一旦考えてみた
〈正解〉D. 情報の真偽について一旦考えてみた
災害時は情報が錯そうするため、デマや誤情報が飛び交います。
特に「すぐに知らせてあげないと」「多くの人に伝えないと」という善意を利用し、フェイクニュースを流布しようとする人もいます。
それにより、混乱や不安を招いたり、本当に必要な救援に関する情報を阻害したり、災害時の限られた通信環境を圧迫するおそれもあるため、注意が必要です。
鵜吞みにせず、情報の真偽を正しく見極めてから情報を共有しましょう!
最後に
大事なことは、防災クイズで何問正解したかではありません。
クイズで問われた知識を災害時に思い出して行動できるかが一番重要です。
さまざまな方法で社内全体の防災意識を向上させて、もしものときに適切な行動が取れる状態をつくっていきましょう!
また、防災訓練や防災対策をレベルアップさせたいとお考えの担当者さまは、弊社が提供する「アドバイザリーサービス」や「防災簡易診断」もご活用ください!
\ 研修で使いたい方、もっと解きたい方はこちら! /