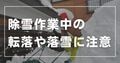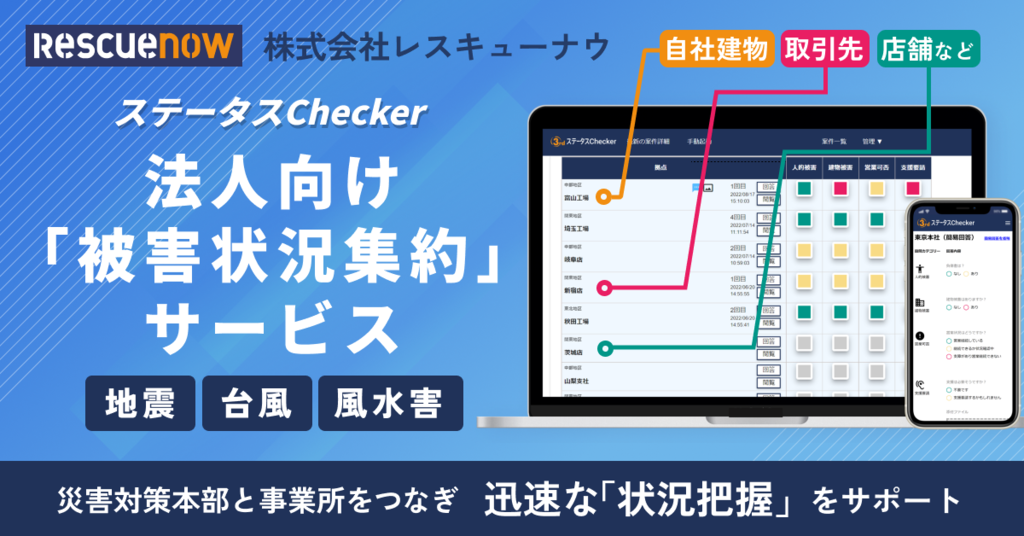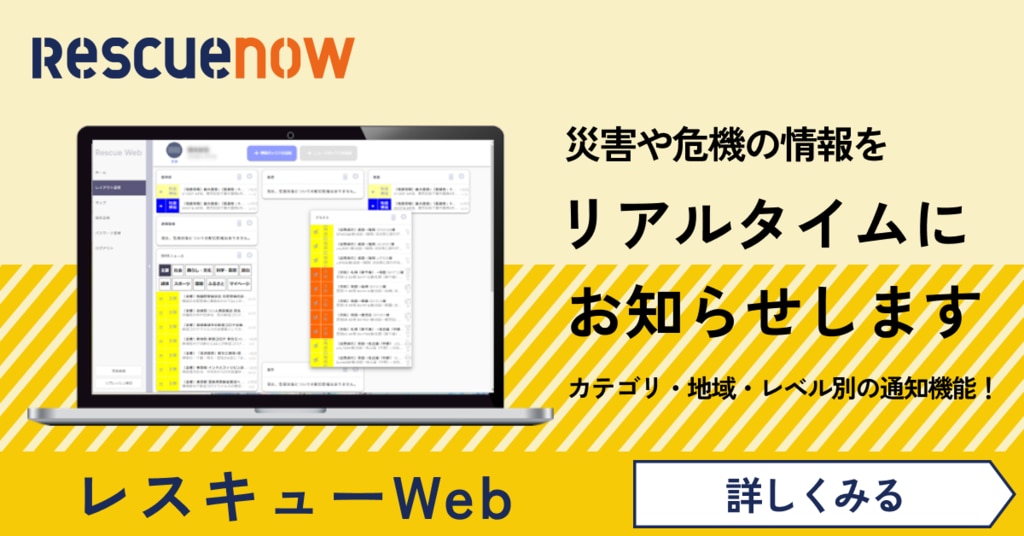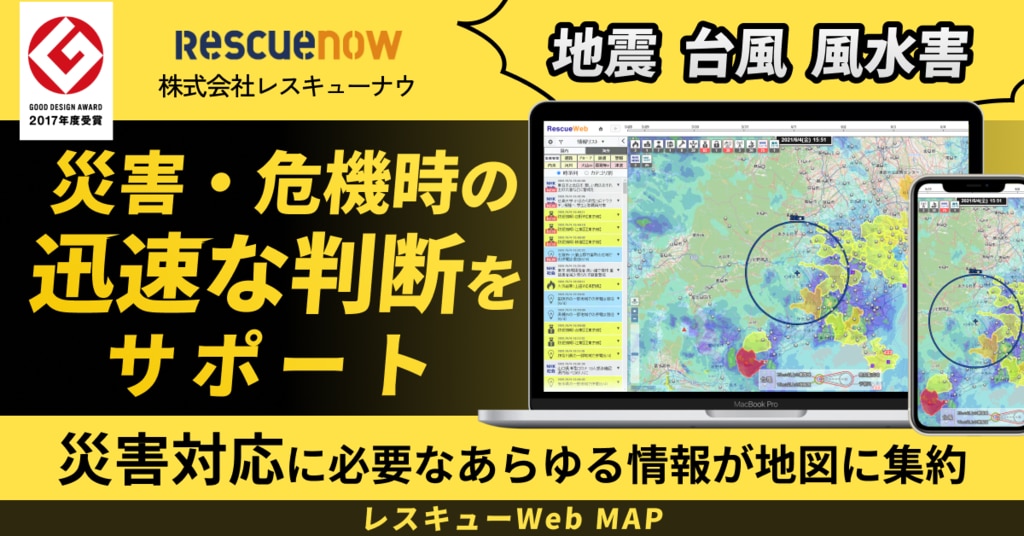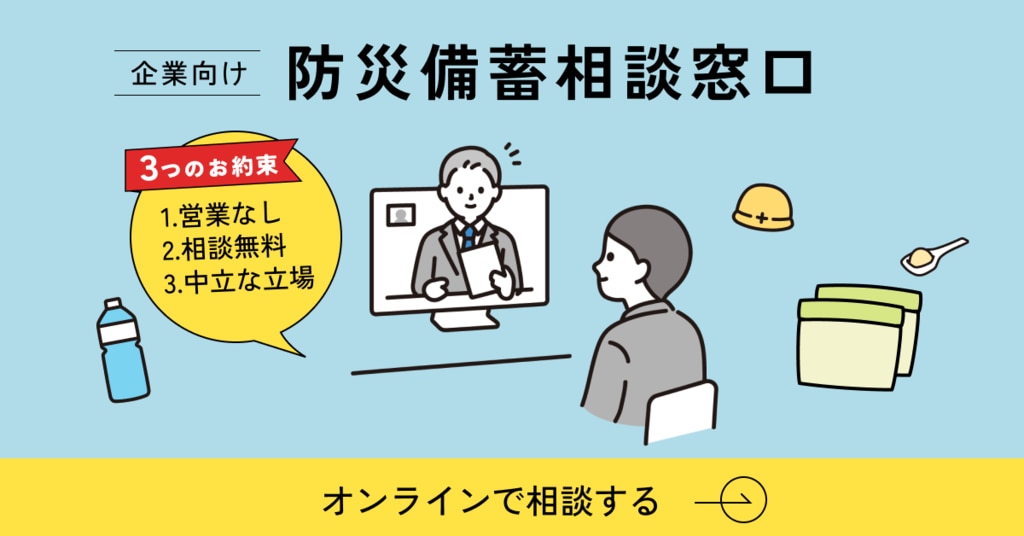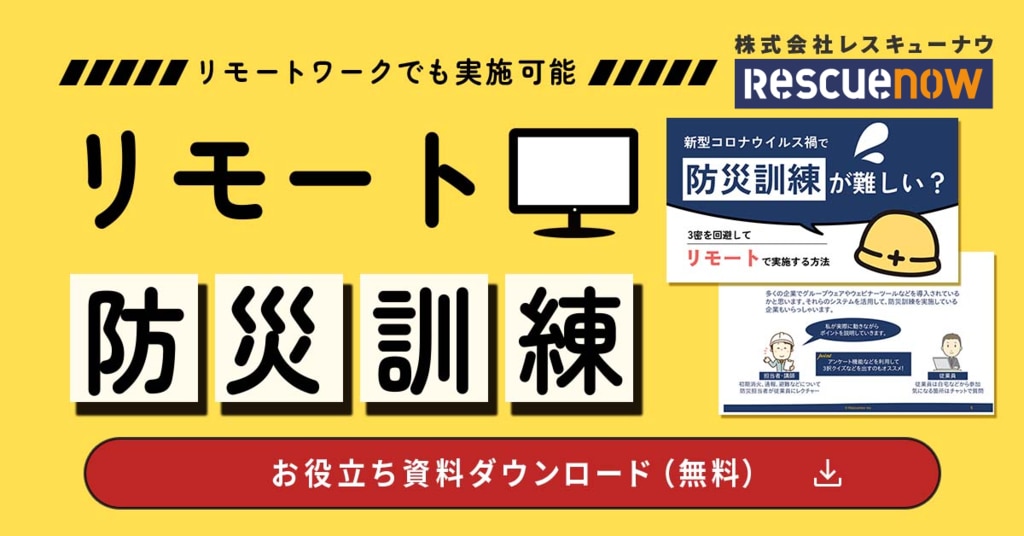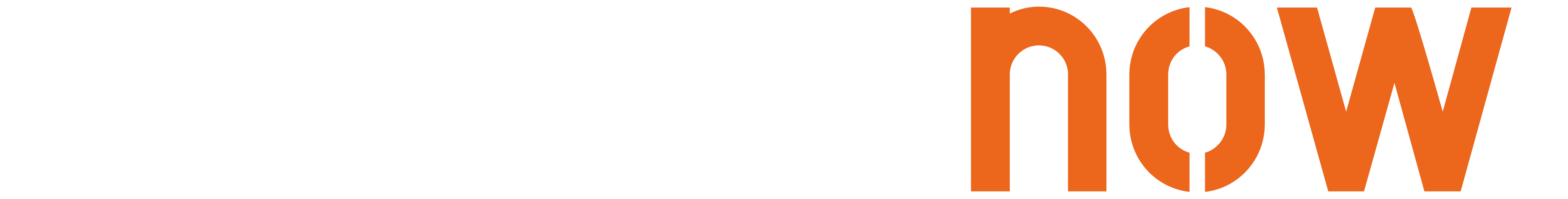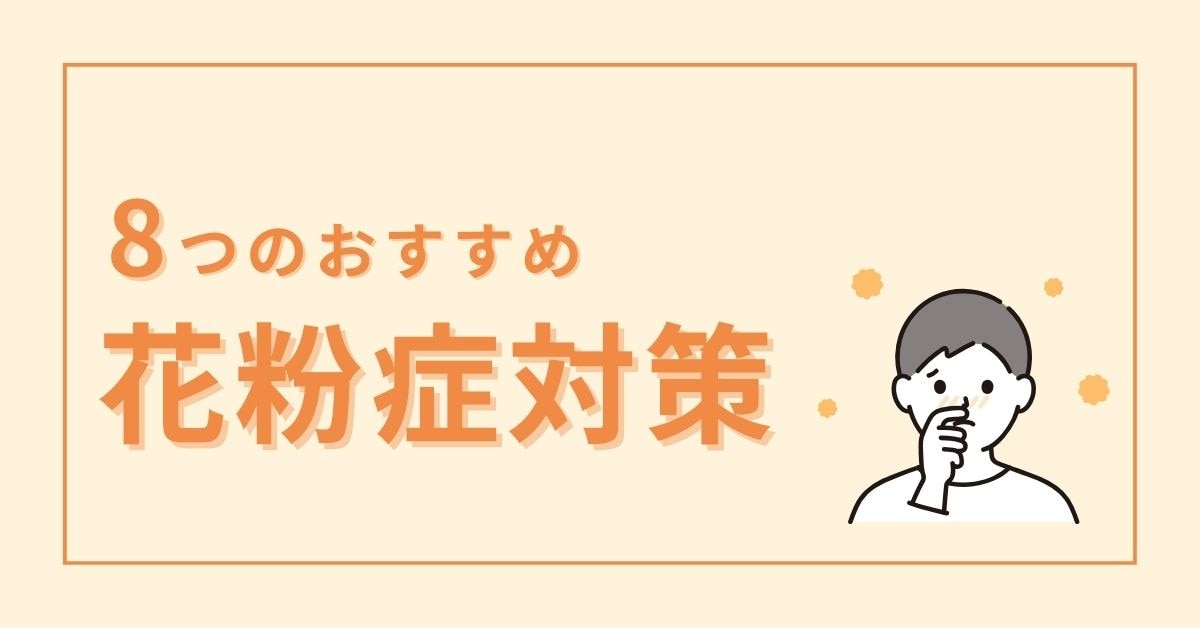
ひどい花粉症を和らげる8つの対策
こんにちは。レスキューナウです。
暦の上では既に春を迎え、早い方だと花粉症の症状に悩まされ始めている頃ではないでしょうか。
日本で花粉症を有する人の正確な数は分かっていませんが、2019年に実施された耳鼻咽喉科医とその家族を対象とした鼻アレルギーの全国調査からは、約3人に1人がスギ花粉症であると推定されています。
例年、スギやヒノキの花粉は4月頃まで飛散するため、花粉によるアレルギー性鼻炎の症状が出る方にとって、これからは憂鬱な季節そのものです。
そこで今回は、日常生活を少しでも快適に過ごしていただくための花粉症対策のポイントや注意点について分かりやすくまとめましたので、「毎年花粉症で悩まされている」という方はぜひご覧ください。
この記事の目次[非表示]
- 1.花粉を「避ける」「持ち込まない」
- 1.1.花粉を避ける
- 1.1.1.マスク、メガネを装着する
- 1.1.2.花粉が大量に飛散する時間帯の外出は避ける
- 1.1.3.テレワークの活用
- 1.2.花粉を持ち込まない
- 1.2.1.花粉が付着しにくい服装選び
- 1.2.2.頭・顔・手に花粉を付けない
- 1.2.3.手洗い・うがい・洗顔・洗髪をする
- 1.2.4.換気方法を工夫する
- 1.2.5.洗濯物や布団の外干しは控える
- 2.快適な職場環境を保つ方法
- 3.喘息持ちの方は要注意
- 4.情報を集めて花粉の飛散状況を知る
- 5.スギ・ヒノキ以外の花粉症
花粉を「避ける」「持ち込まない」
花粉症対策で何よりも重要と言えるのが、可能な限り花粉を「避ける」こと、もしくは「持ち込まない」ことです。
しかしながら、具体的にどのようにすれば花粉を避け、持ち込まないようにできるのかと疑問に感じることもあるかもしれません。
それぞれのポイントについて詳しく確認してみましょう。
花粉を避ける
マスク、メガネを装着する
花粉によるアレルギー症状は、花粉が口・鼻・目から体内に入ることで起きます。
そのため、すでに対策をされている方にとっては当たり前のことですが、口・鼻・目を覆う対策が必要です。
マスクや花粉症対策用のメガネを装着することで、体内に入る花粉を少しでも減らしていきましょう。
花粉が大量に飛散する時間帯の外出は避ける
1日の中で花粉が大量に飛散するピークの時間帯は「昼前後」と「夕方」の2回です。
「昼前後」は早朝に山間部で飛散した花粉が都市部に流れ込み、飛散のピークを迎えます。
また、「夕方」になると太陽が沈んで気温が下がり、空気の対流が生まれます。
その結果、上空の花粉が地上に降りたり、地面に付着していた花粉が舞い上ったりして、飛散がピークを迎えます。
ひどい症状を抑えるために、外出時はできるだけそういった花粉の飛散量が多い時間帯を避けるようにすると良いでしょう。
テレワークの活用
勤務先の理解や支援が前提とはなりますが、花粉の大量飛散が予想される日は、積極的にテレワークを活用するのも一つの対策です。
外出を控えることで花粉を浴びる機会そのものを減らし、症状の悪化を防ぐことができます。
職場のルールを確認しながら、自分に合った働き方を検討してみましょう。
花粉を持ち込まない
花粉が付着しにくい服装選び
屋内に花粉を持ち込まないためには、花粉が付着しにくい服装を選ぶことが大切です。
特にウール素材は花粉が付着しやすいためより一層の注意が必要になりますが、一方で、綿やポリエステルなどの化学繊維は比較的付着しにくいとされています。
外出時の服選びを工夫し、花粉の侵入を最小限に抑えましょう。
頭・顔・手に花粉を付けない
花粉は特に頭・顔・手に付着しやすいため、該当箇所を特にしっかりと対策をすることが重要です。
頭や顔はつばの広い帽子をかぶり、手は手袋を着用することで、花粉が付着する量を抑えることができます。
また、肌に直接花粉が付くのを防ぐために、なるべく露出を控えた服装を心がけましょう。
手洗い・うがい・洗顔・洗髪をする
屋外から屋内に入る際は、手洗いやうがいを徹底しましょう。
さらに、帰宅後すぐに洗顔や洗髪を行うことで、髪や肌に付着した花粉を落とし、屋内への持ち込みを防ぐことができます。
こまめなケアをすることで、症状の軽減につながります。
換気方法を工夫する
換気のため窓を開放する場合は、開ける幅を10cm程度に抑えることが効果的です。
また、レースのカーテンをすることで屋内への花粉の流入を減らすことができます。
なお、 24時間換気システムが設置されている場合は、花粉対応の給気口フィルターを取り付けるのも良いでしょう。
洗濯物や布団の外干しは控える
洗濯物を外干しすると、花粉が付着して室内に持ち込まれる原因となるため、できる限り部屋干しを心がけましょう。
ただし、毎回部屋干しにするのが難しい場合は、コインランドリーの乾燥機を活用する、布団乾燥機や布団クリーナーを使用するといった工夫を取り入れてみてください。
また、外干しした洗濯物は取り込む前に十分にはたくなど、少しの工夫でも室内に入り込む花粉を抑え、快適な生活を保つことができます。
快適な職場環境を保つ方法
ある試算では、花粉症による生産性の低下は1日当たり2,215億円の経済的損失を招くとされており、花粉症は企業の生産活動にも影響を及ぼすことがわかっています。
くしゃみや鼻水、目のかゆみといった症状をできる限り緩和し、仕事に集中するためにもオフィス内での花粉症対策をしっかり行い、快適な職場環境の維持に努めましょう。
オフィス内での花粉症対策においては、特に花粉を「持ち込まない」「拡散させない」ことが重要です。
まず、花粉を持ち込まない工夫として、出勤時には花粉が付きにくいポリエステル素材の衣類を選び、オフィスに入る前に衣類をはたいて花粉を払い落とすことが効果的です。
オフィスの玄関に花粉除去用のマットを設置するのも有効でしょう。
次に、オフィス内での拡散を防ぐためには、空気清浄機や加湿器の活用も有効です。
加湿の場合は、室内の湿度を50〜60%に保つことがポイントで、花粉が空気中に舞い上がるのを防ぐ効果が期待できます。
また、デスク周りのセルフケアとして、作業スペースには小型の空気清浄機を設置すると、周囲の空気を清浄に保つことができます。
花粉症用の目薬や保湿ティッシュも忘れずに常備し、外出後には手洗い・うがい・洗顔・洗髪を行うことで花粉を効果的に落とすことが可能です。
企業によっては、前述した通りテレワークや時差出勤を活用することで花粉を浴びる機会を減らすこともできるため、日常の小さな工夫を積み重ねて、快適な環境を維持しましょう。
喘息持ちの方は要注意
花粉症シーズンは、喘息を持つ方にとって特に注意が必要な時期です。
花粉症が喘息の症状を悪化させることがあり、その背景には花粉表面のアレルゲンが関係していると考えられています。
一般的に喘息の発作が起こりやすい時間帯は午前2時~午前4時頃と言われているため、寝室の清掃や寝具類の洗濯を十分に行い、発作の原因とされるダニや花粉などのアレルゲンを可能な限り除去するとよいでしょう。
なお、最近の研究では、アレルギー性鼻炎の治療を行うことで、気管支の粘膜にも良い影響を与え、気道の過敏性が改善される可能性が示唆されています。
花粉症と喘息は密接に関連しているため、早めの花粉症対策が喘息の悪化を防ぐカギとなります。
医師と相談しながら、症状に合わせた適切な治療を進めていきましょう。
情報を集めて花粉の飛散状況を知る
これまで述べてきた対策を効率的・効果的に行うためには、花粉の飛散状況を把握することが重要です。
花粉の飛散量は天気・気温・風向きによって変動するため、最新の情報を頻繁にチェックしましょう。
行政機関や民間の気象サービスから詳細な花粉情報が提供されているため、自分にとって使いやすい情報源を見つけ、日々の対策に役立てることをおすすめします。
また、春先には中国大陸から黄砂が流れ込むことがあり、この黄砂もアレルギーや喘息を悪化させる要因とされています。
花粉だけでなく大気汚染物質の飛散状況も併せて確認し、より万全な対策を心がけましょう。
スギ・ヒノキ以外の花粉症
花粉症の原因となる植物は、スギやヒノキだけではなく、イネ科・キク科・アサ科の植物も花粉症を引き起こすことで知られています。
特にイネ科の植物は種類が多く、春から初秋にかけて長期間にわたって花粉が飛散します。
さらに、キク科のブタクサやヨモギ、アサ科のカナムグラの花粉は、夏の終わりから秋にかけて飛散のピークを迎えます。
つまり、花粉症を引き起こす花粉は年間を通して飛散しており、季節ごとに異なる植物が症状の原因となる可能性があります。
もし一年中花粉症のようなアレルギー症状が続く場合は、医療機関でアレルギー検査を受け、症状の原因を特定してみることをおすすめします。
また、症状が改善しない場合は、早めに医師に相談し、適切な治療を開始することも検討しましょう。
【おすすめ記事】