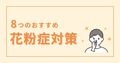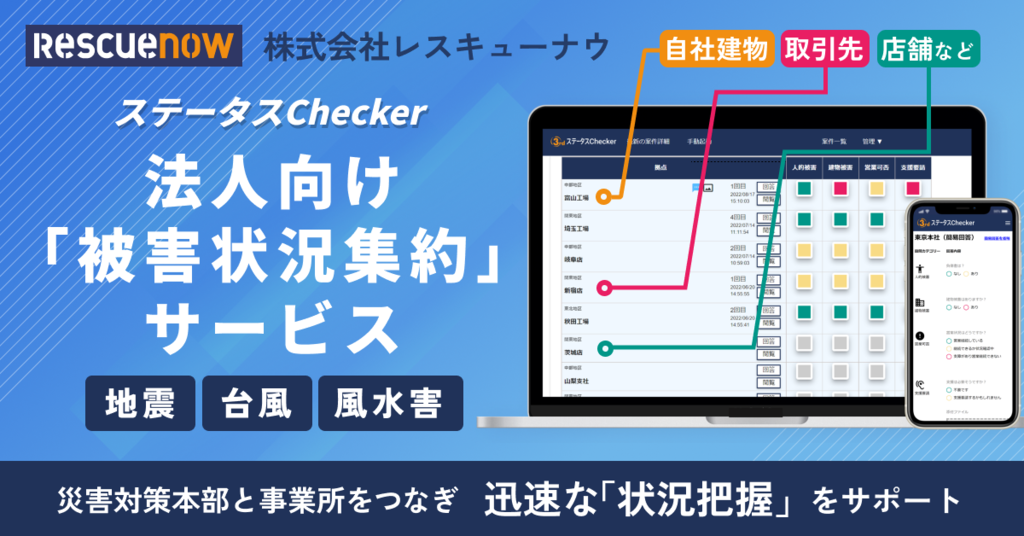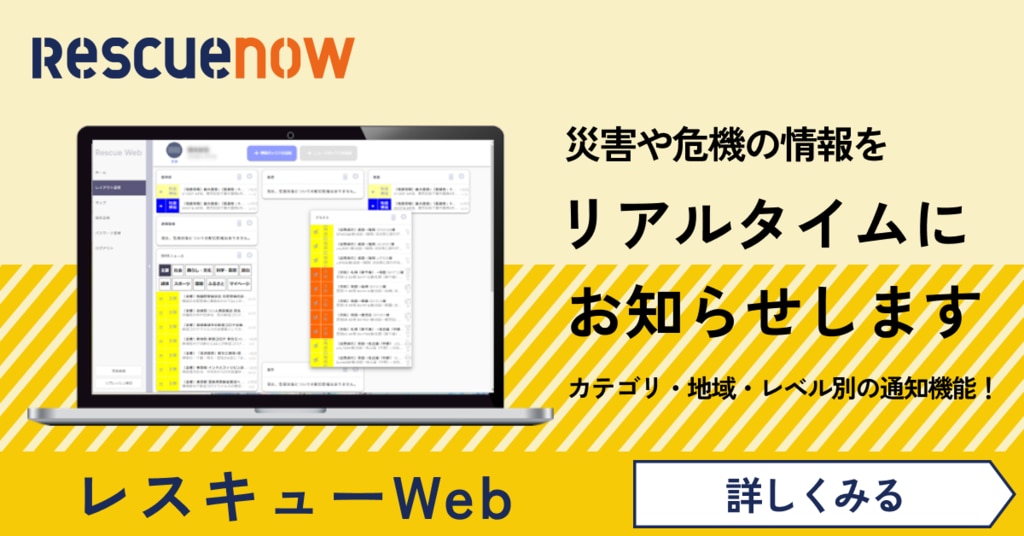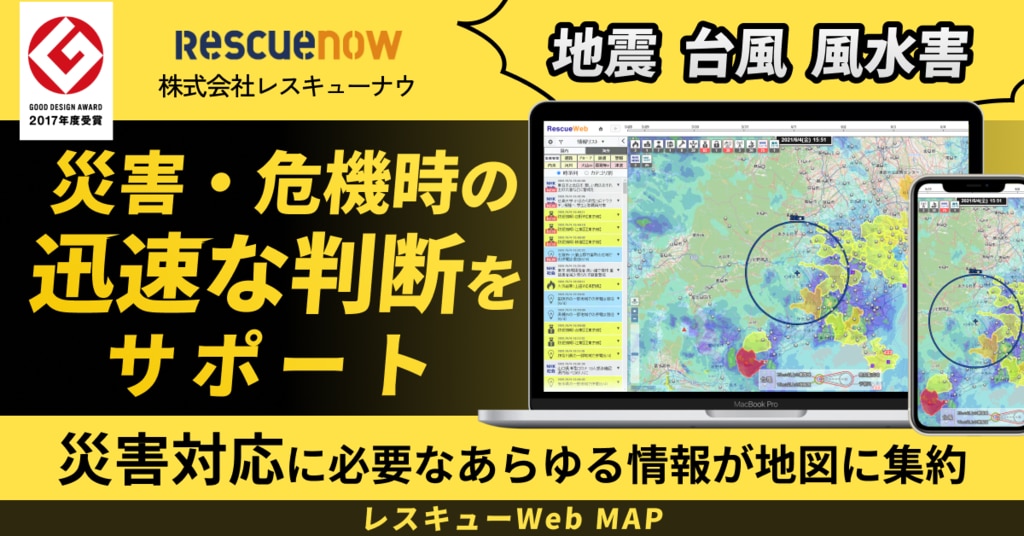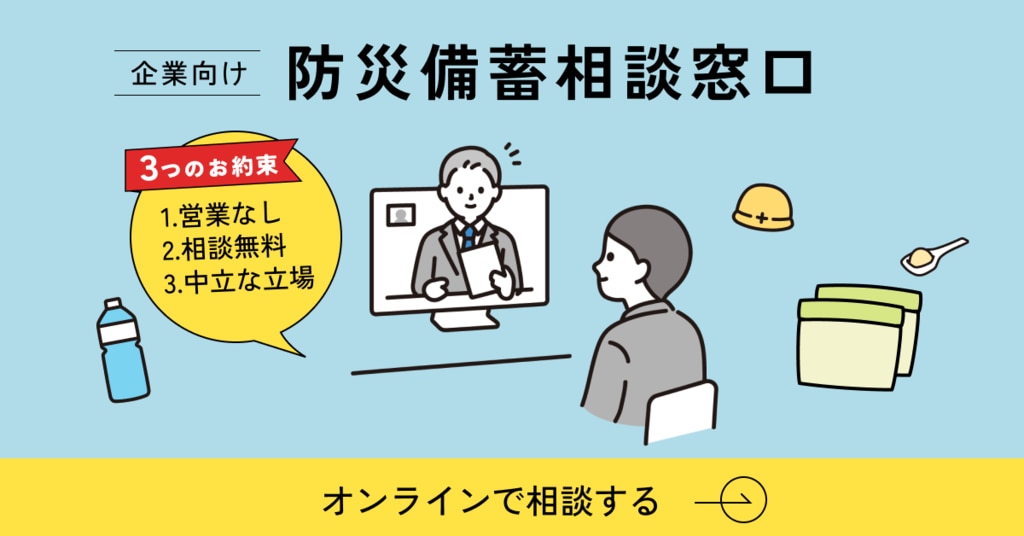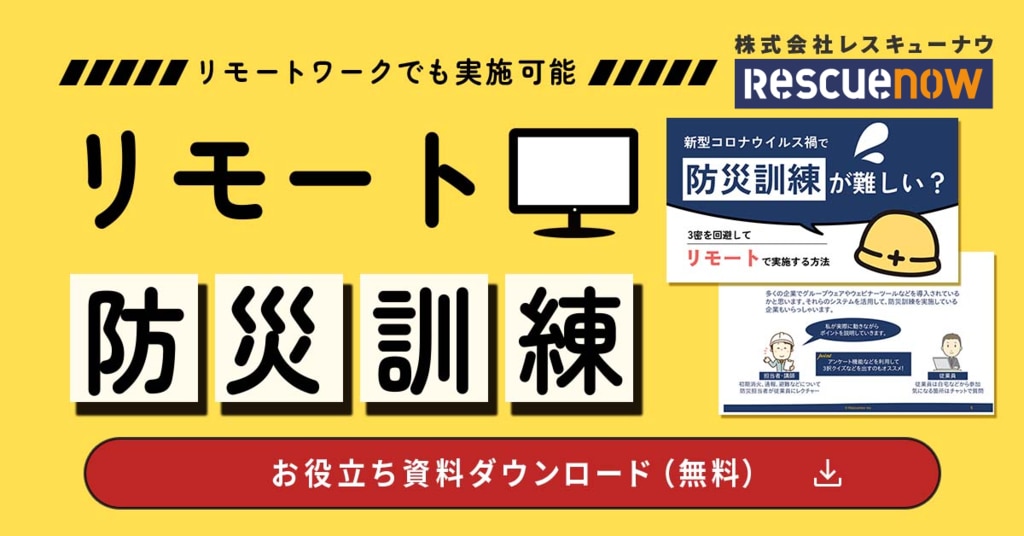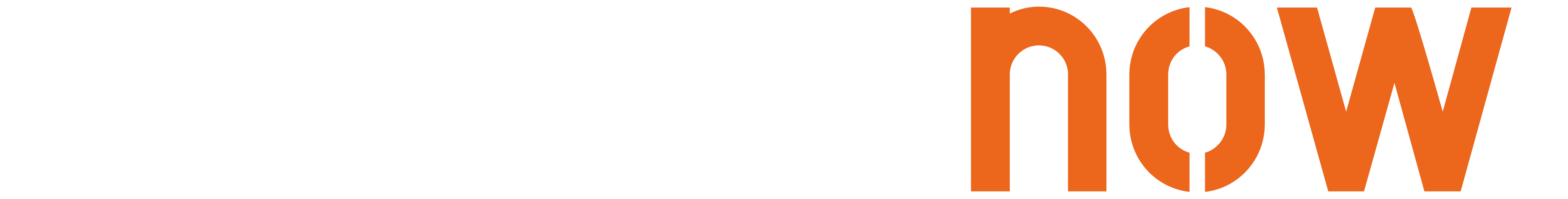【潜入!アドバイザリーの現場②】いざという時、勇気をもって一歩踏み出せますか?
今、あなたの目の前にいる人が突然倒れたとします。
その時、あなたはどのような行動をとれば良いのか、頭にパッと浮かぶでしょうか?
42脚の椅子と8体のマネキンが整然と並べられた、東京都内のとある貸会議室。
そこでは、まさにそういった緊急事態が起こった際の正しい対応を学ぶための訓練が実施されていました。
改めましてこんにちは、レスキューナウの佐藤です。
今回私が潜入してきたのは、とある会社の災害対応訓練の現場。
レスキューナウの「アドバイザリーサービス」では、①体制の構築 ②初動対応手順の策定 ③必要なツールの整備 ④各種訓練の支援 という4つの視点から、企業の災害対応力の向上をサポートしていますが、その中でも特に「訓練支援」についてのご質問をよくいただきます。
そこで今回は、「レスキューナウの防災訓練って、実際にどんなことをするの?」といった皆様の疑問にお応えするために、連結従業員数2,000名規模のN社で実施された「サーキット訓練」に密着してきました。
実際の訓練の様子や、そこから得られた気づきを余すことなくお伝えしますので、防災訓練の見直しやアップデートをお考えの方はぜひ最後までご覧ください。
この記事の目次[非表示]
訓練概要
サーキット訓練とは、複数の訓練メニューを順番に回りながら実施する訓練方式のことで、一般的には体育や筋力トレーニングを指すことが多いですが、防災・危機管理の分野でもこの方式が活用されています。
今回は、合計約1時間の訓練を1回40人程度の参加者で計4回実施。
2日間で合計300名以上が参加しました。
2名の講師がそれぞれのブースを担当し、参加者は順番にブースを回ることで1度に多くの人が複数の訓練メニューを効率的に体験できます。
|
項目 |
時間 |
|---|---|
ガイダンス |
15分 |
応急対応(通報、止血、骨折) |
9分 |
消火(消火器、消火栓、煙避難) |
8分 |
交代 |
1分 |
心肺蘇生(胸骨圧迫、AED) |
18分 |
クロージング |
3分 |
ガイダンス終了後に参加者は2グループに分かれ、一方は会議室前方で応急対応から、もう一方は会議室後方で心肺蘇生から訓練を開始。
途中で前方と後方の参加者が場所を入れ替わり、全員がすべての訓練メニューを体験できるように進めます。
コロナ禍を経て6年ぶりの開催ということもあり、初めて参加される方も多く、開始前の会場には緊張感と真剣な空気が漂っていました。
ガイダンスでは、地震の発生数や活火山の数、断層の数などを振り返り、企業における災害対応力の重要性について改めて考えます。
驚きもなく淡々と話を聞く参加者の様子からは、日本における災害がそれだけ“当たり前の存在”になっているということが感じられ、だからこそ災害に対する備えが必要なのだと深く考えさせられました。
気づきが変える、いざという瞬間
― 応急対応に向ける真剣なまなざし
ガイダンスが終わると、いよいよ訓練開始です。
まずは、緊急時の119番通報の仕方を体験しますが、経験したことがない方にとってはこれが意外と難しいもので、実際に参加者の中には住所を正確に伝えることに苦戦している方も見られました。
そこでの「住所がわからない時は近くの電柱やコンビニの店舗名を確認してみましょう」という講師のアドバイスから新たな学びを得た方もいらっしゃったようです。
また、止血の訓練では“患部を相手の心臓よりも高い位置に持っていく”ということに対して、
-「心臓より高い位置にするの難しくないですか?」
という疑問の声が上がりましたが、
-「止血されている人を座らせ、止血している人が立つと良いですよ」
と講師から伝えられると、即座に実践に移している様子も見受けられました。

人間誰しも経験したことがないことを実践するのは難しいものですが、一度訓練を受けることで、いざという時にその経験を思い出し、適切に対応できるようになります。
改めて、“知識を得ること”や“気づきを得ること”が、いざという時の助けになるということを深く感じました。
「頭でわかる」と「体が動く」は違う
― 体感的に学ぶ初期消火の現場
次に、消火器や消火栓の使い方、火災現場からの避難の仕方を体験する訓練です。

消火器の正しい使い方を動画で学ぶ際には、後方の参加者がスクリーンを覗き込むほど真剣に見ている様子が非常に印象的で、“消火器は先を振るようにして使うと火が消えやすい”という説明に対しては、
-「なるほど...」
と納得の声が漏れていました。
また、衛生管理者をされているという男性は、実際の消火器を使って行う模擬消火訓練の際に参加者全体の中でもひと際スムーズな動きを見せており、こうした現場ではやはり“体験したことがあるか否か”によって大きな差が生まれるということも改めて実感しました。
煙が立ち込めている現場からの避難を想定した訓練では、長テーブルの間にかけられたブルーシートの下を通ることで、その時の態勢を身体に覚えてもらいます。

ブルーシートをかき分けて出てきた参加者からは、
-「思ったよりもきつい態勢で避難しなきゃいけないんだね」
という声も聞かれ、この一言に“頭でわかっている避難”と“実際に体験した避難”とのギャップが現れていることを感じ、理論と実践の違いを強く感じさせられました。
助けるために押し続ける2分間
― 心肺蘇生のリアル
全体を通して、特に盛り上がりを見せたのが心肺蘇生訓練です。
胸骨圧迫の深さは成人の場合、約5センチが目安とされていますが、これを実現するためにはしっかりと体重をかける必要があります。
それを2分間休まずに1分あたり100〜120回(1秒間に約1.5〜2回)のペースで行うのは、想像以上に大変です。

絶え間なく胸骨圧迫を続ける中で、参加者からは時折、
-「これは疲れるね...」
-「ふー…!」
-「え、まだやるの!?」
といった疲れを訴える声も聞こえてきました。
季節は冬。空調は送風にしていたにもかかわらず、顔をあおぐ人もいるほどです。

また、心肺蘇生訓練の最後、講師が参加者に対して会社や家の近くのAEDの設置場所を尋ねると、多くの方が不安そうな表情を見せていたのも印象的でした。
「確認しておいてくださいね」という講師の言葉に参加者は深く頷き、“普段から準備しておくこと”の大切さを再認識しているようでした。
いざという時、勇気をもって一歩踏み出せますか?
すべての訓練メニューが終了すると、講師から改めて「一歩踏み出す勇気を持ちましょう」というメッセージが伝えられます。
また、訓練の最後に用意された“ある仕掛け”によって、参加者の皆さんは“いざという時、自分は本当に行動できるのか?”という問いを、より深く心に刻んでいる様子でした。
やはり、頭では分かっていても、身体がすぐに動くとは限らないもの。
その場にいると、驚きや戸惑いが勝ってしまい、一瞬の躊躇が生まれてしまうこともあります。
潜入した側の私としても、心にとめておきたいメッセージです。
また、N社さんの訓練を実施する姿勢として何よりも印象的だったのは、若手から役員の方まで幅広い層が参加し、組織全体で防災・危機管理の重要性を周知させ、意識向上を図ろうとしていた点です。
特に、役員や管理職が率先して実技に取り組んでいたことは、現場の社員にとって大きな刺激となり、「自分たちもやらなければ」という意識を強く喚起する要因となっていたと思います。
企業の防災対策は、誰か一人が取り組めばよいものではなく、皆で取り組むもの。
防災訓練で得た学びを日常業務にも活かし、“いざという時に一歩踏み出せる勇気”を持てるよう、会社全体での防災意識を高めていくことが求められます。
編集後記
実は、今回の訓練には、実施企業のご厚意により、他社から参加されている方が数名いらっしゃいました。
参加した方からは「消防署や訓練施設で受講したものだけでは、いざという時に動けない従業員が多そうだと実感した」「現在実施しているものは“訓練のための訓練”になってしまっていると改めて感じた」といったお声をいただきました。
その一方で、今回のような全員参加型の実践的な訓練の導入が、課題解決の有効な手段になりそうだとの嬉しい声もいただき、特に短時間で複数の訓練メニューを大人数に対して実施できる点について高く評価いただきました。
自社の防災訓練に課題をお持ちの方には、お役立ち資料もご用意しておりますので、ぜひご覧ください。
▼防災訓練に関する課題の無料相談窓口はこちら▼